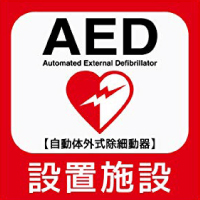親知らずを抜くと起きてしまう可能性のあるトラブルについて今回はまとめていきます。
起きて欲しくはないのでなるべく回避をしたいところです。自分で気をつけられることと気をつけられないこともあるので、親知らずの抜歯を考えている方はぜひ参考にしてください。
親知らずの抜歯後のトラブル
- 腫れと痛み
- 口が開かない、飲み込みしづらい
- ドライソケット
- 口臭
- 上顎洞との交通・親知らずの迷入
- 下歯槽管神経損傷
があります。
それぞれ詳しく説明しますと、
1. 腫れと痛み
親知らずが歯ぐきに少しでも埋まっている場合は、歯ぐきを切って抜いていきます。また、根深い場合や根が曲がっている場合は親知らず周囲の骨も削って抜いていきます。そのため、一時的に炎症が起こり、腫れや痛みがでます。
腫れのピークは術後およそ3日後で、そこから痛みや腫れが引いていきます。個人差もありますので、術後1週間は腫れると思っていて良いでしょう。
2. 口が開かない、飲み込みしづらい
親知らずを抜いた後の起こる炎症と腫れが原因で、口を開けようとすると痛みがでて、開けづらくなります。また、親知らずは喉に近いため、ものを飲み込む時にも痛みが出ることがあるため、飲み込みがしづらくなることがあります。
3. ドライソケット
ドライソケットとは、歯を抜いた場所にうまくかさぶたができず、中の骨が露出した状態のことで、何もしていなくても痛みがでます。術後数日は安静にし、かさぶたができるように優しくお口をゆすぐことと、歯ブラシなどで刺激しないようにしましょう。
もしドライソケットになった場合は歯科医院で適切な処置を行うことで再びかさぶたをつくることができます。
4. 口臭
抜歯後は歯がなくなり、歯ぐきに穴が空いた状態になります。その部分に食べ物が入り込んでしまうと口臭が気になることあります。 しかし、入り込んだものを取ろうとしてかさぶたが剥がれてしまうとドライソケットになってしまうので、気にしないようにしましょう。
傷口が完全に治りますと、口臭も自然と治ります。
5. 上顎洞との交通・親知らずの迷入
上顎の親知らずを抜く際に注意が必要なのが、上顎洞(副鼻腔)です。上顎洞に親知らずの根が刺さっている場合があります。その際、その親知らずを抜きますと、お口の中と上顎洞が交通します。交通すると、水分を飲んだ際にお鼻のほうにまわるということがでてきます。交通が小さい場合は放置していても治りますが、大きな場合は交通を治すための処置が必要になります。
安静にしていれば自然と治りますが、お口や鼻に圧をかける行為(強く鼻をかむ、風船をふくらませる等)がありますと、治りかかっているものが再び交通することになりますので、注意しましょう。また、ごくまれに親知らずが上顎洞の中に入ってしまうということもあります。そのようなことが起こってしまった場合は大学の口腔外科を紹介させていただきます。
6. 下歯槽管神経損傷
下歯槽管神経損傷とは、下顎の親知らずを抜く際に起きてしまう可能性があるものです。親知らずの近くに下歯槽管神経が走行しています。その神経を親知らずを抜く際に傷つけてしまうと、麻痺がおこってしまいます。この際は大学病院などの麻酔科にて、神経節ブロックを行ったり、温熱療法などを行い、麻痺を治していきます。また、ビタミン剤を飲んでいただくこともあります。
治療にはスピードが必要です。抜歯の翌日に麻痺が確認できたらすぐにこれらの処置を行っていきましょう。
歯科治療による
下歯槽神経・舌神経損傷の診断と
その治療に関するガイドライン
まとめ
いかがでしたでしょうか。
親知らずの抜歯だけではなく、歯科治療は外科的な処置が多いです。そのため、メリットも大きいですが、デメリットも生じてきます。デメリットを知った上で治療をうけることはとても重要です。
少しでもわからないことがあったら、歯科医院で、歯科医師にしっかり確認するようにしましょう。